目的
Stefan-Boltzmannの法則とは、黒体が放射するエネルギー量とその物体の表面温度との関係が次のように示される物理法則である。黒体とはすべての波長において入射する放射を完全に吸収する理想的な物体を指す。
\begin{align}
w_\mathrm{em}=\sigma T^4
\end{align}
ただし、$w_\mathrm{em}$ [W/m$^2$]は単位面積、単位時間あたりに放射されるエネルギーであり、$T$ [K]は黒体の絶対温度である。また、$\sigma$はStefan-Boltzmann定数であり、$\sigma\simeq 5.67\times10^{-8}$ $[\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot \mathrm{K}^{-4}]$である。
この法則は、熱放射に関する研究の歴史の中で重要な役割を果たし、熱力学および量子力学の発展に寄与した。19世紀後半、熱放射の研究は急速に進展した。1879年、オーストリアの物理学者J. Stefanは、実験的な結果に基づき、黒体から放射されるエネルギーがその絶対温度$T$の4乗に比例することを示した。この法則はStefanの法則として知られる。1884年には、Stefanの弟子であるL. Boltzmannが、熱力学と電磁気学の理論を用いて、この結果を理論的に導出した。Boltzmannの研究により、この法則が物理学的に深い意味を持つことが明らかとなり、以後Stefan-Boltzmannの法則として知られるようになった。
ここでは、電磁気学と熱力学のみを用いて、$w_\mathrm{em}\propto T^4$となることを示す。具体的には、電磁場の運動量をもとに黒体の空洞内における放射エネルギーを計算し、熱力学第1,2法則により絶対温度と関連付ける。
Stefan-Boltzmannの法則は、星や惑星の放射特性を理解するための基盤となる。例えば、恒星の表面温度を推定する際や地球の放射平衡を解析する際に利用される。また、熱放射の研究は、後にPlanckの黒体放射公式や量子力学の誕生にもつながった。そこで、最後にはStefan-Boltzmannの法則の応用例として、最も単純に太陽を黒体と仮定し、太陽の表面温度を推測してみる。これが、現在の知見で分かっている実際の温度にどれだけ近いかどうかを議論して終える。
導出の手順
ここで既知と仮定するのは、電磁気学におけるMaxwell方程式と熱力学における第1、2法則のみである。ただし、一部の議論では、Maxwell方程式の電磁ポテンシャルを用いた表現と、放射ゲージを採用する。ここは数学的な手法に過ぎないため、Maxwell方程式を知っていれば十分である。その他は、すべて導出していくが、同様にベクトル解析などについても数学的な処理のため証明を省く。しかし、特に難しい計算はないため、初めて見る場合でも自分で計算すれば確かめられる程度である。
導出の手順として、まずはじめに電磁波の運動量が$\bm{G}_\mathrm{f}=\frac{1}{c^2}\int_V\dd^3x\,\bm{S}(\bm{x},t)$と書けることを示す。ここで現れる$\bm{S}$はPoyntingベクトルであるが、これについても紹介する。そのあとに、電磁場のエネルギー密度が$w_\mathrm{em}=\frac{1}{2}\left(\bm{E}\cdot\bm{D}+\bm{B}\cdot\bm{H}\right)$と表せることを示す。次にこれらを平均値としてみると$\bar{|\bm{S}|}=c\bar{w}_\mathrm{em}$の関係が成り立つことを示す。ここまでが事前準備であり、必要となる電磁波の性質を電磁気学の範疇で導出しておく。
次にStefan-Boltzmannの法則を示すための問題設定として、空洞内の電磁波について考える。そこで、電磁波の運動量、エネルギー密度、Poyntingベクトルとそれらの平均値の関係を利用して、電磁波のエネルギー密度と力積の関係を導く。これにより、電磁波を光子気体とみなした場合の圧力を、電磁波のエネルギー密度を用いて表現することができる。ここまではすべて電磁気学の範疇で、光子気体の状態方程式が得られたことになる。
最後の手順として、熱力学の議論に移り、熱力学の第1、2法則:$T\dd S=\dd W+p\dd V$に対して光子気体の状態方程式を代入する。これにより、電磁波のエネルギー密度$w_\mathrm{em}$と光子気体の温度$T$の関係が、$w_\mathrm{em}\propto T^4$となることが示される。
電磁場の運動量の導出
以下のMaxwell方程式から議論を始める。
\begin{align}
&\divergence\bm{D}(\bm{x},t) =\rho_\mathrm{e}(\bm{x}),\label{eq: maxwell1_inChapMaxwell}\\
&\rot\bm{E}(\bm{x},t)+\del{\bm{B}(\bm{x},t)}{t} =0,\label{eq: maxwell2_inChapMaxwell}\\
&\divergence\bm{B}(\bm{x},t)=0,\label{eq: maxwell3_inChapMaxwell}\\
&\rot\bm{H}(\bm{x}, t)-\del{\bm{D}(\bm{x},t)}{t}=\bm{i}_\mathrm{e}(\bm x, t).\label{eq: maxwell4_inChapMaxwell}
\end{align}
点電荷系($i=1,2,\dots,n$)と電磁場が存在する系を考える。このとき、自己力も含んだ点電荷の運動方程式は、
\begin{align}
m_i\ddif{\bm{r}_i(t)}{t}=\int_V\dd^3x\left(q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\bm{E}(\bm{x},t)+q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\dot{\bm{r}}_i(t)\times\bm{B}(\bm{x},t)\right)
\end{align}
である。ここで、すべての点電荷について$i$の和をとると、
\begin{align}
\sum_im_i\dif{\bm{v}_i(t)}{t}&=\sum_i\int_V\dd^3x\left(q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\left\{\bm{E}(\bm{x},t)+\dot{\bm{r}}_i(t)\times\bm{B}(\bm{x},t)\right\}\right)\nonumber\\
&=\sum_i\int_V\dd^3x\left(\bm{E}(\bm{x},t)\divergence\bm{D}(\bm{x},t)+\left(\rot \bm{H}(\bm{x}, t)-\del{\bm{D}(\bm{x},t)}{t}\right)\times\bm{B}(\bm{x},t)\right)
\end{align}
とできる。ただし、$\sum_iq_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))$は点電荷系がつくる電荷密度であるため、Maxwell方程式の第1式および第4式より以下のように書ける。
\begin{align} \sum_iq_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))&=:\rho\mathrm{e}(\bm{x},t)=\divergence \bm{D}(\bm{x}, t),\\
\sum_iq_i\dot{\bm{r}}i(t)\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))&=:\bm{i}\mathrm{e}(\bm{x},t)=\rot \bm{H}(\bm{x}, t)-\del{\bm{D}(\bm{x},t)}{t}.
\end{align}
また、
\begin{align}
\del{}{t}\left(\bm{D}\times\bm{B}\right)=\del{\bm{D}}{t}\times\bm{B}+\bm{D}\times\del{\bm{B}}{t}=\del{\bm{D}}{t}\times\bm{B}-\bm{D}\times\rot\bm{E}
\end{align}
とすることで式を整理すると、
\begin{align}
&\dif{}{t}\left(\bm{G}\mathrm{m}(t)+\frac{1}{c^2}\int_V\dd^3x\,(\bm{E}\times\bm{H})(\bm{x},t)\right)\nonumber\\ &\quad=\int_V\dd^3x\left(\bm{E}(\bm{x},t)\divergence\bm{D}(\bm{x},t)-\bm{D}(\bm{x},t)\times\rot\bm{E}(\bm{x},t)-\bm{B}(\bm{x},t)\times\rot\bm{H}(\bm{x},t)\right)\label{eq: em_field_mom_eq1} \end{align}
まで変形できる。右辺の形にするときにも、Maxwell方程式の第2式を利用した。 ただし、全点電荷系の運動量を$\bm{G}_\mathrm{m}:=\sum_im_i\bm{v}_i(t)$と書いた。 我々はこの方程式をNewton方程式などとの類推により運動量保存として解釈することができる。 つまり、運動方程式を変形して得られたこの式は、「左辺の運動量の時間変化が、右辺の力に等しい」と解釈できる。このとき、左辺の第2項は電磁場のもつ運動量を表すことになる。この中に現れる$\bm{S}:=\bm{E}\times\bm{H}$はPoyntingベクトルと呼ばれるものであり、これを用いて、
\begin{align} \bm{G}_\mathrm{f}:=\frac{1}{c^2}\int_V\dd^3x\,\bm{S}(\bm{x},t)\label{eq: def_Gf_mom}
\end{align}
と書ける。これが電磁場の運動量である。
ちなみに、式\eqref{eq: em_field_mom_eq1}の右辺については、ここでは議論しないがMaxwellの応力テンソルと呼ばれるもので簡単に表せ、電磁場に働く力と解釈できるものである。
電磁場のエネルギーの導出
続いて、再び運動方程式から出発して、今回はエネルギー保存の式を見る。
運動方程式は、
\begin{align}
m_i\ddif{\bm{r}_i(t)}{t}=\int_V\dd^3x\left(q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\bm{E}(\bm{x},t)+q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\dot{\bm{r}}_i(t)\times\bm{B}(\bm{x},t)\right)
\end{align}
と書ける。この両辺に速度ベクトル$\bm{v}_i(t)=\dd \bm{r}_i(t)/\dd t$との内積をとって$i$について和をとると、第2項が直交するために消えて、
\begin{align}
&\sum_im_i\bm{v}_i(t)\cdot\dif{\bm{v}_i(t)}{t}=\sum_i\int_V\dd^3x\left(q_i\delta^{(3)}(\bm{x}-\bm{r}_i(t))\bm{v}_i(t)\cdot\bm{E}(\bm{x},t)\right)
\end{align}
を得る。
ここでも、電流密度が現れるので、Maxwell方程式の第4式を用いると、
\begin{align}
\sum_i\dif{}{t}\left(\frac{1}{2}m_i\bm{v}_i^2(t)\right)&=\int_V\dd^3x\left(\rot \bm{H}(\bm{x}, t)-\del{\bm{D}(\bm{x},t)}{t}\right)\cdot\bm{E}(\bm{x},t)\nonumber\\
&=\int_V\dd^3x\left(\bm{E}(\bm{x},t)\cdot\rot \bm{H}(\bm{x}, t)-\del{\bm{D}(\bm{x},t)}{t}\cdot\bm{E}(\bm{x},t)\right)\nonumber\\
&=\int_V\dd^3x\left(-\frac{1}{2}\del{}{t}\left(\bm{E}\cdot\bm{D}+\bm{B}\cdot\bm{H}\right)-\bm{H}\cdot\rot\bm{E}+\bm{E}\cdot\rot\bm{H}\right)
\end{align}
まで変形できる。ただし、最後の式変形では、
\begin{align}
\frac{1}{2}\del{}{t}\left(\bm{E}\cdot\bm{D}+\bm{B}\cdot\bm{H}\right)=\bm{E}\cdot\del{\bm{D}}{t}+\bm{H}\cdot\del{\bm{B}}{t}
\end{align}
と、Maxwell方程式の第2式から、$\partial\bm{B}/\partial t=\rot\bm{E}$を用いた。
ベクトル恒等式:
\begin{align}
\divergence\left(\bm{E}\times\bm{H}\right)=\bm{H}\cdot\rot\bm{E}-\bm{E}\cdot\rot\bm{H}\label{eq: vec_div_ExH}
\end{align}
を用いると、最終的に運動方程式は次の形まで変形できる。
\begin{align}
\dif{}{t}\left[\sum_i\dif{}{t}\left(\frac{1}{2}m_i\bm{v}_i^2(t)\right)+\frac{1}{2}\int_V\dd^3x\left(\bm{E}\cdot\bm{D}+\bm{B}\cdot\bm{H}\right)\right]=-\int_V\divergence\left(\bm{E}\times\bm{H}\right)\dd^3x.
\end{align}
この式もNewton方程式などの類推により、物理学ではエネルギー保存の式であると解釈する。いま考えていたのは点電荷系と電磁場からなる系であったが、それらを分離することに成功している。左辺の第1項は全点電荷系の運動エネルギーを表している。古典力学の範疇なら、運動エネルギーの時間変化はなす仕事の量に等しいはずである。しかし、いま考えている電磁気学においては、2つの電磁場に関係する項が存在する。まず、左辺の時間微分を含むものは電磁場のもつエネルギーであると解釈できる。そして右辺は、Gaussの定理を用いると領域$V$の表面$S$における面積分に変わり、
\begin{align}
-\int_V\divergence\left(\bm{E}\times\bm{H}\right)\dd^3x=-\int_S \bm{S}\cdot\bm{n}\dd S
\end{align}
となる。これは電磁場に関するベクトル量である$\bm{S}$が、領域$V$から湧き出す(抜け出ていく)量を表す。この物理量$\bm{S}$を、前節でも導入したがPoyntingベクトルという。すなわち、電磁場のエネルギーの流れを表す。このPoyntingベクトルなる量が、表面$S$の法線ベクトル成分の値をもつとエネルギーの流れが存在することになり、全エネルギーが減少することを意味する。
以上の結果をまとめると、電磁場のエネルギー$U_\mathrm{em}$の表式は次のように得られた。
\begin{align}
U_\mathrm{em}(t)&:=\int_Vw_\mathrm{em}(\bm{x},t)\dd^3x,\\
w_\mathrm{em}&:=\frac{1}{2},\left(\bm{E}(\bm{x},t)\cdot\bm{D}(\bm{x},t)+\bm{B}(\bm{x},t)\cdot\bm{H}(\bm{x},t)\right)
\end{align}
ただし、$w_\mathrm{em}$は電磁場のエネルギー密度である。
Poyntingベクトルと電磁場エネルギーの平均値
さて、ここまでで電磁場の運動量、エネルギー、およびPoyntingベクトルの表式が得られた。次に、いよいよStefan-Boltzmannの法則に入るための準備として、Poyntingベクトルと電磁場のエネルギー密度の平均値どうしの関係式を導出する。まず、Poyntingベクトルの平均値として、
\begin{align}
\bar{\bm{S}}=\frac{1}{\mu_0}\overline{\bm{E}\times\bm{B}}\label{eq: def_ave_poyn}
\end{align}
と書ける。同様に、電磁場のエネルギー密度の時間平均は、
\begin{align}
\bar{w}_\mathrm{em}=\frac{1}{2}\left(\overline{\bm{E}\cdot\bm{D}}+\overline{\bm{B}\cdot\bm{H}}\right)\label{eq: def_ave_wem} \end{align} と書ける。これら2つの間には、$\bar{|\bm{S}|}=c\bar{w}_\mathrm{em}$の関係が成り立つ。このことを示すために、具体的な平面波としての電磁波を例に考える。ここからは自由場を考え、$\rho_\mathrm{e}=0$および$\bm{i}_\mathrm{e}=\bm{0}$とする。
自由場のMaxwell方程式を電磁ポテンシャルによる表現に書き換え、適切なゲージ変換により放射ゲージと呼ばれる条件にとることで以下のようになる。
\begin{align}
&\bm{E}(\bm{x},t)=-\del{\bm{A}_\mathrm{r}(\bm{x},t)}{t},\label{eq: maxwell_radcond1}\\
&\bm{B}(\bm{x},t)=\nabla\times\bm{A}_\mathrm{r}(\bm{x},t),\label{eq: maxwell_radcond2}\\
&\left(\Delta-\frac{1}{c^2}\ddel{}{t}\right)\bm{A}_\mathrm{r}(\bm{x},t)=\bm{0},\label{eq: maxwell_radcond3}\\ &\nabla\cdot\bm{A}_\mathrm{r}(\bm{x},t)=0.
\end{align}
電磁波の振る舞いを調べるときに、この放射ゲージを採用すると静電ポテンシャルが消え、ベクトルポテンシャルのみで表せるため計算上都合がよい。
\begin{align}
\left(\Delta-\frac{1}{c^2}\ddel{}{t}\right)\bm{A}=0
\end{align}
と書ける。
この波動方程式の解として最も単純な平面波解を考えると、
\begin{align}
\bm{A}(\bm{x},t)=\bm{e}_1a_k(t)\mathrm{e}^{i\bm{k}\cdot\bm{x}}
\end{align}
と書ける。ベクトルポテンシャルの向く方向の単位ベクトルを$\bm{e}_1$とした。このとき、$\bm{x}$は長さの次元を持つため、$\bm{k}$は波数(ベクトル)を表す。
これを元の波動方程式に代入すると、
\begin{align}
0=\left(\Delta-\frac{1}{c^2}\ddel{}{t}\right)\bm{A}=-\bm{e}_1\left(k^2a_k(t)+\frac{1}{c^2}\ddel{a_k(t)}{t}\right)\mathrm{e}^{i\bm{k}\cdot\bm{x}} \end{align} となる。当然ながら$\bm{k}\cdot\bm{x}\neq0$なる平面波解に興味があるので、振幅$a_k(t)$が満たすべき方程式として、
\begin{align}
k^2a_k(t)+\frac{1}{c^2}\ddel{a_k(t)}{t}=0
\end{align}
が得られる。この解は、
\begin{align} a_k(t)=a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{-i \omega t}, \ \ \ \ \omega:=c|\bm{k}|
\end{align}
と書ける。
つまり、ここまでで
\begin{align}
\bm{A}(\bm{x},t)=\bm{e}_1a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}
\end{align}
のように表せた。
これが放射ゲージのもとでのベクトルポテンシャルだとすれば、
\begin{align}
0=\divergence\bm{A}(\bm{x},t)=i(\bm{e}_1\cdot\bm{k})a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}
\end{align}
より、ベクトルポテンシャルの方向$\bm{e}1$と、波数ベクトルの方向$\bm{k}$は直交することが分かる。また、
\begin{align} &\bm{E}(\bm{x},t)=-\del{\bm{A}(\bm{x},t)}{t}=i\bm{e}_1 \omega a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)},\\
&\bm{B}(\bm{x},t)=\nabla\times\bm{A}(\bm{x},t)=i\bm{e}_2ka_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)},
\end{align}
である。ここで、$\bm{e}_2:=(\bm{k}/k)\times\bm{e}_1$で新たな単位ベクトルを導入した。$\bm{E}$は$\bm{e}_1$と同じ方向、つまりベクトルポテンシャルとも同じ方向であり、$\bm{B}$は$\bm{e}_1$とも$\bm{k}$とも直交する方向であることが分かる。
この表現を用いて、式\eqref{eq: def_ave_poyn}に代入し、複素表現の実部のみをとって1周期$T=2\pi/\omega$で平均をとると、
\begin{align}
\bar{\bm{S}}&=\frac{1}{\mu_0}\overline{\bm{E}\times\bm{B}}\nonumber\\
&=\frac{1}{\mu_0T}\int_0^T \mathrm{Re}\,\left(i\bm{e}_1 \omega a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}\right)\times\mathrm{Re}\, \left(i\bm{e}_2ka_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}\right)\dd t\nonumber\\
&=\frac{1}{\mu_0T}\int_0^T \bm{e}_3\omega k |a_{\bm{k}}|^2\sin^2\left(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t\right)\dd t\nonumber\\
&=\bm{e}_3\frac{\omega k|a_{\bm{k}}|^2}{\mu_0T} \int_0^T \sin^2\left(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t\right)\dd t\nonumber\\
&=\bm{e}_3\frac{\omega k|a_{\bm{k}}|^2}{\mu_0} \frac{1}{2}=\frac{ck^2}{2\mu_0}|a_{\bm{k}}|^2\bm{e}_3 \end{align}
を得る。同様に、式\eqref{eq: def_ave_wem}に代入し、複素表現の実部のみをとって1周期$T=2\pi/\omega$で平均をとると、 まず、1項目が
\begin{align} \overline{\bm{E}\cdot\bm{D}}&=\frac{1}{T}\int_0^T \left(\mathrm{Re}\,\bm{E}\cdot\mathrm{Re}\,\bm{D}\right)\dd t\nonumber\\
&=\frac{\varepsilon_0}{T}\int_0^T\left[\mathrm{Re}\,\left(i\bm{e}_1 \omega a_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}\right)\right]^2\dd t\nonumber\\
&=\frac{\varepsilon_0\omega^2|a_{\bm{k}}|^2}{T}\int_0^T \sin^2\left(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t\right)\dd t\nonumber\\
&=\frac{\varepsilon_0\omega^2|a_{\bm{k}}|^2}{2}
\end{align}
となり、全く同様に2項目は、
\begin{align}
\overline{\bm{B}\cdot\bm{H}}&=\frac{1}{T}\int_0^T \left(\mathrm{Re}\,\bm{B}\cdot\mathrm{Re}\,\bm{H}\right)\dd t\nonumber\\
&=\frac{1}{\mu_0T}\int_0^T\left[\mathrm{Re}\,\left(i\bm{e}_2ka_{\bm{k}}\mathrm{e}^{i(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t)}\right)\right]^2\dd t\nonumber\\
&=\frac{k^2|a_{\bm{k}}|^2}{\mu_0T}\int_0^T \sin^2\left(\bm{k}\cdot\bm{x}-\omega t\right)\dd t\nonumber\\
&=\frac{k^2|a_{\bm{k}}|^2}{2\mu_0}
\end{align}
となる。
よって、
\begin{align}
\bar{w}_\mathrm{em}&=\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon_0\omega^2|a{\bm{k}}|^2}{2}+\frac{k^2|a_{\bm{k}}|^2}{2\mu_0}\right)=\frac{k^2}{2\mu_0}|a_{\bm{k}}|^2=\frac{1}{c}|\bar{\bm{S}}|
\end{align}
を得る。したがって、目的としていた
\begin{align}
\bar{|\bm{S}|}=c\bar{w}_\mathrm{em}\label{eq: def_S_cw}
\end{align}
が得られた。
空洞内の電磁波の状態方程式
ここまでで、ようやくStefan-Boltzmannの法則の導出するための準備ができた。
式\eqref{eq: def_Gf_mom}より、電磁波の運動量は、
\begin{align}
\bm{G}_\mathrm{f}:=\frac{1}{c^2}\int_V\dd^3x\,\bm{S}(\bm{x},t)
\end{align}
であり、ここに含まれるPoyntingベクトルと電磁波のエネルギー密度$w\mathrm{em}$の間には式\eqref{eq: def_S_cw}より次の関係が成り立つ。
\begin{align}
\bar{|\bm{S}|}=c\bar{w}_\mathrm{em}.
\end{align}
いま、一辺の長さが$L$の立方体(体積$V=L^3$)の形をした空洞を考える。すなわち、この内部は真空である。この中で光が放射するエネルギーを考える。空洞内の平均運動量は、Poyntingベクトルと同じ方向の単位ベクトルを$\bm{e}$とすると、
\begin{align}
\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f}}=\frac{1}{c^2}\int_V\dd^3x\,\bar{|\bm{S}|}\bm{e}=\frac{1}{c}\bar{w}_\mathrm{em} V\bm{e}
\end{align}
である。
この空洞内で適当にある方向を決めて$x$軸とし、この$x$軸と$\bm{e}$のなす角を$\theta$とすれば、
\begin{align}
\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}=\frac{1}{c}\bar{w}_\mathrm{em} V\cos\theta
\end{align}
と書ける。この空洞内は真空であるため、電磁波は速さ$c$で進む。この空洞内の$x$軸方向と空洞の壁が接する点の1つを開始地点とし、逆側の端で反射して元の位置に戻ってくるまでの往復を考える。すると、距離は$2L$であり、速さは$c\cos\theta$であるから、この往復にかかる時間は$2L/(c\cos\theta)$である。このときに運動量の損失はないため、運動量変化は
\begin{align}
\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}-(-\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x})=2\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x} \end{align} である。よって、単位時間あたりの運動量変化は、
\begin{align} 2\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}\times\left(\frac{2L}{c\cos\theta}\right)^{-1}=\frac{\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}c\cos\theta}{L}
\end{align}
であり、これが空洞の壁に与える力である。つまり、このとき壁の圧力$p_x$は、上記の力を壁の面積$L^2$で割ることで、
\begin{align} p_x=\frac{\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}c\cos\theta}{L^3}
\end{align}
となる。よって、これを空洞内の全角度で平均をとることにより全体の圧力$p$が得られる。
\begin{align}
p&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\dd\theta\int_0^{2\pi}\dd\phi \frac{\bar{\bm{G}}_{\mathrm{f},x}c\cos\theta}{L^3}\nonumber\\&=\bar{w}_\mathrm{em}\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\dd\theta=\bar{w}\mathrm{em}\left[-\frac{1}{3}\cos^3\theta\right]^{\pi/2}_0=\frac{1}{3}\bar{w}_\mathrm{em}
\end{align}
ここまでで、空洞内の電磁波の圧力とエネルギーの関係式が得られた。これは真空中の光子気体が満たす状態方程式に相当する。ここまでは電磁気学から得られる結論である。
Stefan-Boltzmannの法則の導出
さて、状態方程式が得られたら電磁気学とは関係なく、熱力学の知識を利用できる。熱力学の法則から、
\begin{align}
T\dd S=\dd W+p\dd V\label{def: netsu12}
\end{align}
の関係が成り立つ。まず、先ほどまで考えていた問題設定と結びつけるためには、$W=\bar{w}_\mathrm{em}V$とすればよい。さらに、$\dd W$を$V,T$を変数とした形に書き換えると、 \begin{align} \dd W=\bar{w}_\mathrm{em}\dd V+\dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}V\dd T \end{align} 式\eqref{def: netsu12}より、先ほど得られた$p=\bar{w}_\mathrm{em}/3$を代入し、
\begin{align}
\dd S=\frac{4}{3}\frac{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}\dd V+\frac{V}{T}\dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}\dd T=\left(\del{S}{V}\right)\dd V+\left(\del{S}{T}\right)\dd T
\end{align}
となる。そして、最後に、
\begin{align}
\del{}{T}\left(\del{S}{V}\right) = \del{}{V}\left(\del{S}{T}\right)
\end{align}
から、
\begin{align}
\del{}{T}\left(\del{S}{V}\right) &=\del{}{T}\left(\frac{4}{3}\frac{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}\right)=-\frac{4}{3}\frac{\bar{w}_\mathrm{em}}{T^2}+\frac{4}{3}\frac{1}{T}\dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}\\
\del{}{V}\left(\del{S}{T}\right) &=\del{}{V}\left(\frac{V}{T}\dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}\right)=\frac{1}{T}\dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T} \end{align}
により、最終的に、
\begin{align} \dif{\bar{w}_\mathrm{em}}{T}=4\frac{\bar{w}_\mathrm{em}}{T} \end{align}
となる。この微分方程式を解けば、
\begin{align} \frac{\dd \bar{w}_\mathrm{em}}{\bar{w}_\mathrm{em}}=4 \frac{\dd T}{T} \end{align}
から、 \begin{align} \ln \bar{w}_\mathrm{em}=4\ln T
\end{align}
であり、
\begin{align}
\bar{w}_\mathrm{em}=\sigma T^4
\end{align}
を得る。ただし、$\sigma$は$T$に依らない定数である。最後に得られたこの関係式が、Stefan-Boltzmannの法則で主張する内容である。最後の定数$\sigma\simeq 5.67\times10^{-8}$ $[\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot \mathrm{K}^{-4}]$は、Stefan-Boltzmann定数と呼ばれ、具体的な表式は統計力学的手法によりPlanckの法則から導かれる。
応用例:太陽を黒体と仮定した場合の表面温度
せっかくここまできたので、簡単な応用例として太陽の表面温度を計算してみる。
太陽を黒体であると仮定して、太陽の表面の温度と太陽が放射するエネルギーの関係がStefan-Boltzmannの法則に従うとする。測定された放射エネルギーから表面温度を算出したいが、すべてのエネルギーは測定できないため、等方的に放射されたエネルギーのうち地球で測定されたものから推測する。
地球上で太陽からの放射に対して垂直な面における単位面積あたり単位時間あたりに受けるエネルギーを太陽定数$E_\mathrm{sc}$といい、その値は$E_\mathrm{sc}=1.37\times10^3$ W/m$^2$である。太陽と地球の間の距離を$L_\mathrm{SE}=1.496\times10^{11}$ m、太陽の半径を$R_\mathrm{sun}$とすると、太陽が単位時間あたりに放射するエネルギー$W_\mathrm{total}$は、
\begin{align}
W_\mathrm{total}=4\pi L_\mathrm{SE}^2E_\mathrm{sc}=4\pi R_\mathrm{sun}^2\sigma T_\mathrm{sun}^4
\end{align}
と書ける。最後の式は、太陽の表面温度を$T_\mathrm{sun}$ Kとして
Stefan-Boltzmannの法則を用いた。
上記の関係式より、太陽の表面温度は、
\begin{align}
T_\mathrm{sun}=\sqrt[4]{\frac{E_\mathrm{sc}}{\sigma}\frac{L_\mathrm{SE}^2}{R_\mathrm{sun}^2}}\simeq5780\ \mathrm{K}
\end{align}
となる。実際の表面温度は、5772 Kであり近い値を推測できていることが分かる。


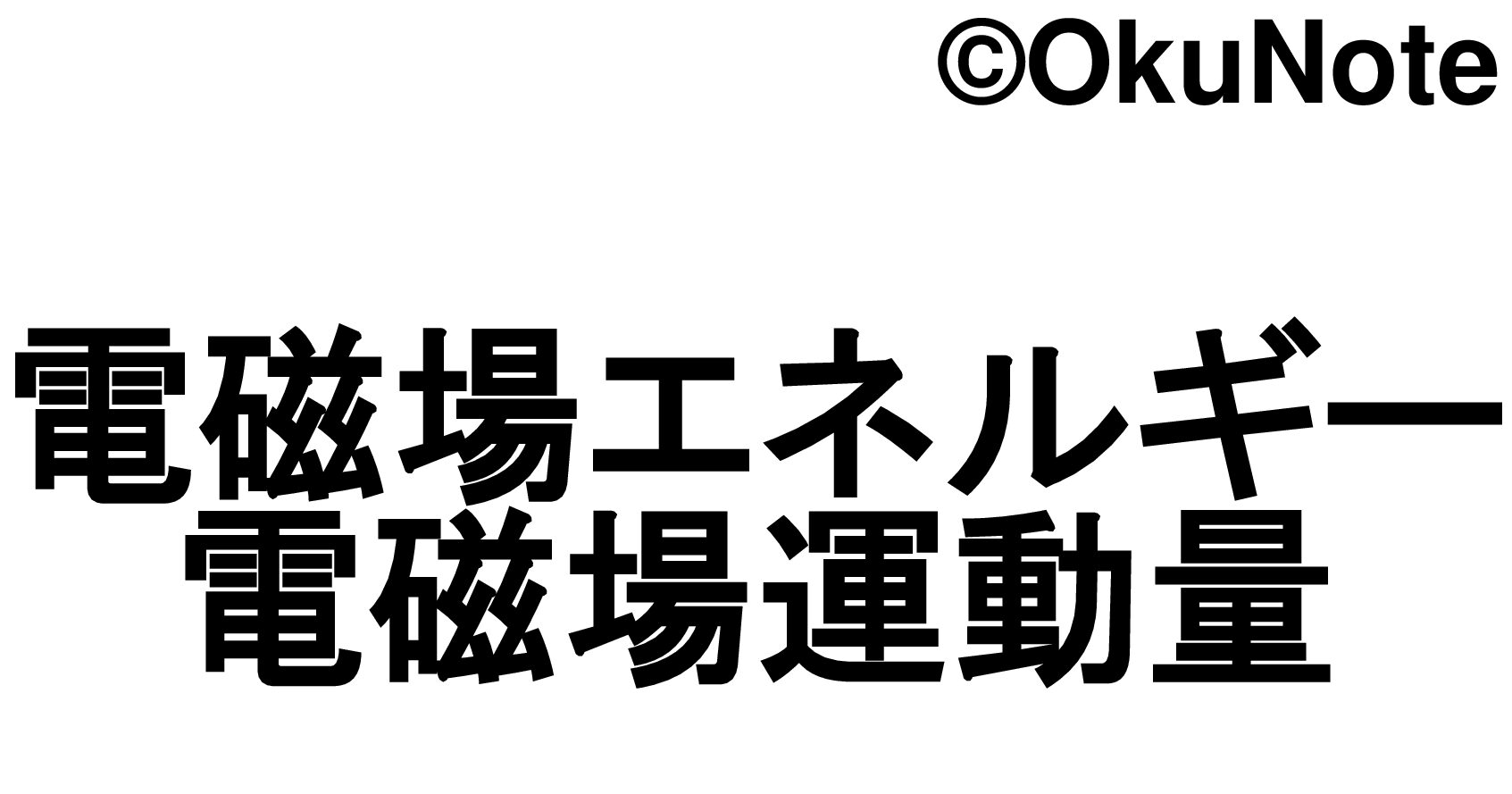
コメント